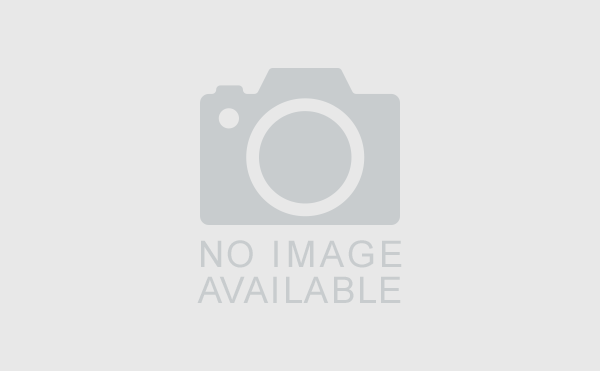声明
水は自治、足下への回帰を
2025年1月28日、埼玉県八潮市内で埼玉県が管理する流域下水道の管路の破損に起因すると見られる道路陥没が発生し、市民に甚大な影響を及ぼした。陥没に巻き込まれたトラックドライバーの一刻も早い救出とともに、事態の収束が望まれたが、残念なことに5月2日遺体で引き上げられた。亡くなられた方のご家族や関係者の皆様に心より哀悼の意を示すものである。
今回の事故は、事故対応において災害救助法が適用されたことからも未曾有の事故といえる。流域下水道の幹線下流部に位置する、シールド工で布設された土被り10メートルを超える内径4750mmの管路が破損したことは、水の現場を預かる誰もが、その重大さに震撼するところとなった。当該事故においては、約120万人を対象とする過去に類を見ない下水道の使用自粛要請が出され、また、下水道の使用ばかりでなく日々の営みや暮らしに重大な影響を及ぼしている。ドライバーの救出と陥没箇所と管路の復旧、そして汚水の輸送機能が失われた中で、市民の衛生と水環境への影響を最小限とするべく現場作業に奔走する私たち全水道の仲間をはじめ多くの方々の努力に敬意を表するとともに、これ以上の二次災害は絶対に招いてはならない。
しかし、こうした事故が生じた中で、収束の展望が不透明であるばかりか、原因究明すらもままならない現状にあることは、甚だ遺憾と言わざるを得ない。何よりも、本来、命を守る「衛生」が責務であるはずの下水道が市民の生命・財産を脅かす存在となってしまったという事実は、これまでの下水道インフラの整備、管理のあり方への反省を突きつけるものであることは間違いない。国土交通省においては、下水道管路の緊急点検を行うとともに、同種の事故を未然に防止するための有識者会議を設置するなど、当該事故を踏まえた対策を図っているところではあるが、管路に起因する大事故の発生は我々だけではなく、事業現場を預かる者が長年警鐘を鳴らし続けていた課題であり、〝遅きに失した〟との思いを強くしている。今般の事故は下水道管路に起因するものであるが、下水道だけでなく水道においても、その資産の大部分は地中に埋設された管路であり、この管路が老朽化し、適切な管理すらままならない現実が顕在化しつつある。
近年、政府は水道・下水道事業のアウトソーシング、PPP/PFIの導入など、民間化・民営化を主導してきた。これに対し全水道では、長年にわたり現場労働者の人員削減が続いてきたことへ危機感、行き過ぎた合理化が招く施設・管路管理のリスクを強く主張してきたが、まさに訴え続けた危機が露わになったものと認識している。今般の事故を受けて2月15日に埼玉県から国土交通省に行った要望においては、国が進めるウォーターPPPの再検討と下水道事業の国庫補助要件からの除外を求めている。
下水道・水道ともに、今見つめるべきは足下にある。水循環基本法の目的とする健全な水循環の維持、回復、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に、下水道・水道が果たす役割が大きいことは言うまでもないが、健全な水循環が社会インフラの足下から崩壊しつつある事実を受け止め、政策の方向性の転換を強く望むものである。
埼玉県の流域下水道は、大阪府に続き全国で第二に長い歴史を有するものである。流域下水道の整備にあたっては、古くからその管理に懸念が示され、論争ともなった。下水道管路破損の上流には、下水道の使用自粛を強いられた12市町、約120万人の暮らしが存在している。下水道使用自粛と合わせて、緊急放流としてほぼ未処理の汚水が公共用水域に放流される事態にも至った。全水道では、「水は人権であり、究極の自治である」ということを強く訴えてきたが、今般の事故は、自治における汚水処理のあり方を再考するうえでも多くの教訓を与えている。行き過ぎた利益の追求や合理化などがもたらした弊害として直視すべきである。
全水道は、あらためて事業現場の労働の重要性を訴えるとともに市民、利用者に寄り添った地に足の着いた水道・下水道政策、水循環政策への転換を強く望むものである。
2025年5月15日
全日本水道労働組合
|