| 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
12月19日、連合主催による「非正規・正規のカベを超えて~雇用危機にどう立ち向かうか?~」をテーマにシンポジウムが開催され、構成組織の仲間など250人が参加した。 冒頭、基調提起を行った古賀伸明・連合事務局長は、急激に悪化する雇用情勢を受けた連合のこの間の取り組みについて報告するとともに、今後の非正規雇用に関する労働組合の取り組み強化を訴えた。 冒頭、基調提起を行った古賀伸明・連合事務局長は、急激に悪化する雇用情勢を受けた連合のこの間の取り組みについて報告するとともに、今後の非正規雇用に関する労働組合の取り組み強化を訴えた。このなかで古賀事務局長は、「連合が実施した緊急雇用相談からも、あまりにも安易に非正規労働者が切り捨てられている現状が浮かび上がっている。確かに今回の雇用危機の背景には世界的な経済情勢があるが、経営側は、すべてを経済の悪化に責任転嫁し、あまりにも簡単に雇用調整に頼りすぎてはいないか。経営も雇用確保の社会的責任を果たすべきである」と指摘した。  そのうえで古賀事務局長は、労働組合、連合としての課題について触れ、「労働組合としての対応が厳しく問われていることを、われわれは強く認識しなければならない。目の前で、昨日まで同じ職場で働いていた仲間が、非正規というだけで何の保障も得られないまま次々と職を奪われていく。これを黙って見過ごすことは許されない。この認識に立って「すべての働く者のために」という視点で、非正規・正規のカベを超え、さらにカベをなくしていく取り組みが必要だ」と訴えた。 そのうえで古賀事務局長は、労働組合、連合としての課題について触れ、「労働組合としての対応が厳しく問われていることを、われわれは強く認識しなければならない。目の前で、昨日まで同じ職場で働いていた仲間が、非正規というだけで何の保障も得られないまま次々と職を奪われていく。これを黙って見過ごすことは許されない。この認識に立って「すべての働く者のために」という視点で、非正規・正規のカベを超え、さらにカベをなくしていく取り組みが必要だ」と訴えた。続いてパネル討論が行われ、龍井葉二・連合非正規労働センター総合局長をコーディネーターに、鹿嶋敬・実践女子大学教授、佐藤久美子・市川市保育関係職員労働組合書記長、安永貴夫・情報労連書記長、浅田明廣・連合北海道非正規労働センター長の各氏がパネリストとして参加し、現在の職場・地域で起きている問題、労働組合としての課題を議論した。 |
|||||||
| 2 | |||||||
|
|||||||
 年末からこの正月にかけて、東京日比谷公園で派遣村を開設した派遣村実行委員会の主催による、「やっぱり必要!派遣法抜本改正1・15集会―派遣村からの大逆襲―」が日本教育会館で開催された。会場のキャパシティが300人のところに400人が集まり、マスコミを含め、会場からあふれるかえるほどの参加者が集まった。 年末からこの正月にかけて、東京日比谷公園で派遣村を開設した派遣村実行委員会の主催による、「やっぱり必要!派遣法抜本改正1・15集会―派遣村からの大逆襲―」が日本教育会館で開催された。会場のキャパシティが300人のところに400人が集まり、マスコミを含め、会場からあふれるかえるほどの参加者が集まった。集会は全国ユニオン鴨代表の司会で始まり、政党より菅直人・民主党代表代行、福島瑞穂・社民党党首、志井和夫・共産党委員長、鈴木宗男・新党大地代表等の野党党首クラスが出席、「野党が結束をして、与党も巻き込んで、なんとしても派遣法の抜本改正を行う」とした決意が述べられた。国民新党や公明党からもメッセージが寄せられた。 労働団体からとして、連合から団野副事務局長が挨拶をおこない、全労協、全労連からもあいさつがおこなわれた。派遣村へ入った村民からは、「職を失い、自殺を考えて出かけた。駅でテレビを見て、気がついたら派遣村に居た」「1月20日から生活保護を受けられる様になり就職をして自立する。これから、こうした取り組みがあったら、今度は助ける番だ」との発言には、会場より大きな拍手が送られた。 最後に、この問題はこれだけでは終わらない。この春は年の瀬を超える大量の『派遣・期間工切り』が予想される。「トヨタの足下、名古屋でも派遣村の準備が進んでいる」と報告がされ、「全国へ広げよう」と呼びかけられた。 新自由主義者の「自己責任論」に対して、「助け合いの社会」をどう作るかを鋭くつきだした闘いである。こうした闘いに、私たち組織された労働者が地域でどう連帯するかが、今問われている。 |
|||||||
| 3 | |||||||
|
|||||||
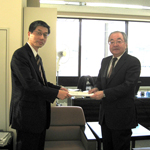 厚労省要請 厚労省要請現下の厳しい非正規労働者等の雇用問題への対応が喫緊の課題である中、内閣府・地方分権改革推進委員会が、労働者・国民の立場からは問題ともいえる内容を含んだ「第2次勧告」を取りまとめた(12月8日)ことなどの諸状況を踏まえ、12月25日、連合は厚生労働省に対し、労働行政の充実・強化に関する要請を行った。 連合の古賀事務局長が、厚生労働省の小野政策統括官に要請書を手渡し、意見交換を行った。 連合が今回要請したのは、(1)都道府県労働局のブロック化により、労働行政の後退とならない体制整備、(2)雇用対策における都道府県との連携強化、(3)ハローワークの全国ネットワークの維持及び体制の拡充・強化、(4)公共職業訓練の機能強化、(5)地方における労働行政の充実、(6)労働教育の拡充、(7)障害者雇用対策の強化の7項目。 政党要請 連合は、古賀事務局長を代表に、12月18日に民主党と国民新党に、翌19日には自民党、公明党、社民党に対して、当面の経済・財政運営および今年度の第2次補正予算と2009年度予算編成に関する要請を行った。 |
|||||||
| 4 | |||||||
|
|||||||
| 全水道青年女性部を中心に、7月18日に沖縄県議会において決議された「辺野古基地建設反対」の沖縄県議会決議を尊重し、国会・政府に対して〈辺野古に基地をつくってはいけない〉と強く訴える、請願署名を全国の地本・県支部・単組の皆さんに取り組みをお願いしてきました。 昨年末に集約を終了し、全水道全体で59単組より、団体署名86筆、個人署名12,514筆を数え、呼びかけ団体である『辺野古への基地建設を許さない実行委員会』にお渡ししました。 確定・年末闘争の最中、取り組み期間が短かったにもかかわらず、多くの組合員の皆さんに取り組んでいただけたことに感謝申し上げるとともに、報告とさせていただきます。ありがとうございました。 団体署名 86筆 個人署名 12,514筆 |
|||||||
| 5 | |||||||
|
|||||||
| はじめに 日本経団連は、2008年12月16日に「09年版日本経団連・経営労働政策委員報告」を発表した。「労使一丸で難局を乗り越え、さらなる飛躍に挑戦を」とサブタイトルを付けている。一昨年までの「好景気」の際には、労働者の犠牲の上に自分たちだけの「希望の国日本」を唱い上げていたものが、昨年9月のリーマンブラザースの破綻以降の世界的金融危機を受けての景気の一挙的後退局面に入るやいなや、今度は「労使一丸となって難局を乗り越え」と身勝手を言い出している。 この02年からの経団連の「経労委報告」は、それまでの春闘対策のための日経連「労問研報告」を引き継ぎ、03年「春闘の終焉宣言」し労働組合対策に勝利宣言を行った。04年からは国際資本の利害防衛を中心にすえたグローバル化への国内対策と新しい国作りにも踏み込んだ内容のものとなっていった。小泉、安倍と続いた新自由主義路線の構造改革の下、憲法改悪をはじめとした「この国の形」を「希望の国日本」とした。しかし、08年報告ではこの「希望の国日本」の記述は見られなくなる。米国のサブプライムローンの焦げ付きがはじまり、新自由主義路線の矛盾としての格差社会に批判が出始めたからである。そして、今回のリーマンブラザースの破綻によりその矛盾が一挙的に露呈した。 新自由主義は80年代のスタグフレーション(=景気の後退とインフレの同時進行)に対して、サッチャー、レーガンが進めた政策で、「市場原理を万能」とし、市場の競争の中へすべて委ねれば、経済が活性化し、社会が発展すると言うものだった。それは「機会の平等」として経済的・社会的規制をなくし、企業が何処へでも出て行ける体制を作り、国境を越えたグローバル社会を作り出した。そして、企業はその利益を労働者や社会のために還元せず、もっぱら資本家・株主への配当に回した。そしてこのカネが米国の土地を基礎にした金融商品へまわり、カジノ経済とも言える金融経済が異様に膨らみだした。その結果、03年の資料でも世界の実体経済が36兆ドル(3600兆円)に対して、金融経済は130兆ドル(1京3000兆円)と膨らみ、これが今回のリーマンブラザースの破綻で崩壊がはじまったのである。今日では4倍以上の金融経済を実体経済で支えること自体、無理がある。そして、その原因を作りだしカジノ経済へ資金を送り続けたのは、米国や日本の経済界をはじめ世界のグローバル企業の経営者たちである。その救済を私たちの資金である税に求めるのは厚顔無恥としか言いようが無い。まして、ワーキングプアや過労死ぎりぎりまで働かせておいて、自らのみが生き延びるために雇用責任をないがしろにし、内定取り消し、派遣・期間工切り、本工を含む労働者の解雇を行うことは許すことが出来ない。 1・09年版経労委報告の概要 昨年の08年版経労委報告の構成は、第1章「わが国経済をめぐる環境と課題」第2章「日本型雇用システムの新展開と労使交渉・協議に向けた経営側のスタンス」第3章「生産性向上・多様な働き方を可能にする制度の整備」の3部構成であった。09年度版では、序文にはじまり第1章「日本経済を取り巻く環境の変化と今後の見通し」第2章「今次労使交渉・協議における経営側のスタンスと労使関係の深化」第3章「公正で開かれた人事・賃金システムの実現」第4章「わが国企業の活力・競争力を高める環境の整備」としており、4部構成になっている。 第1章は、情勢分析だが「今後の見通し」を付け加えた。第2章には、労使一丸となるためには、「労使関係の深化」としなければならない。第3章では人事・賃金システムが「整備」から「実現」に変わっている。能力・評価制度の賃金システムが一般化し、全体化していることへの自信が伺われる。第4章は「わが国企業の活力・競争力を高める環境の整備」として、あらたに社会・政治制度に注文を付けている。 今年の特徴は、序文で「企業の社会的責任」と「企業倫理」について多くをさいて記載されているが、本文の何処にも触れられていない。触れることができなかったのか。それとも、社会的責任も倫理感もかなぐり捨てて、労働者の首切りを行うと言う決意なのか。いずれにしても、この社会的経済的危機に対して自らを犠牲にしても立ち向かう姿勢は何処のも見えない。 2・09年版日本経団連・経労委報告批判 (1)経済情勢の分析について 報告書では、「金融危機の短期的な解決は期待しがたく、米国経済の回復には相当の時間が必要と考えられる」としており、欧州経済についても、中国などの新興国の経済についても同様で、世界全体の動きである認識を示した上で「世界経済の回復には少なくとも今後数年を要することを覚悟する必要がある」としている。国内経済についても「日本経済は当面、内外需とも牽引材料がまったく見当たらない状況にあり、回復までに相当の期間を要することとなろう」としている。「完全失業率は、02年5・4%から07年3・6%まで回復したが、09年度は5%台と見込まれる」としている。経団連主要メンバー自らが契約期間内の派遣社員を切りはじめ、今春はどう見ても失業者が街にあふれる。しかも、宿舎住まいも追い出されこの年末年始は各地で労働組合、自治体やボランティアの「命の支援」としての炊き出しや越冬テント村の取り組みが行われた。しかし、経団連に参加している主要企業のこうした活動への参加を聞いたことがない。 (2)賃金と経営側の基本姿勢について 第2章・第3章では、「1973年の第一次オイルショックの際、74年大規模なストライキによって32・9%の大幅な賃上げとなった」とし、「1991年の第2次オイルショック、バブル崩壊後の平成不況の際は、経営の再構築=リストラクチェアリング(リストラ)を行い、生産性の向上、国際競争力の強化が出来た」としている。今回も「一層の飛躍へ向けた、たえざる挑戦を続けていく」として、現行の派遣切り、期間工切りなど、どんどんやれとしている。 第2章の冒頭で「これまで日本企業は雇用維持・安定に努めてきており、それが人的資本の蓄積となったほか、労使の信頼関係の構築や従業員の忠誠心・チームワークの土台となり、競争力の源ともなっていた」としている。これは高度成長期の30年も前の話であり、これを日経連自らが95年の労問研報告で「新時代の日本的経営」として、大リストラ=解雇を実行し雇用を不安定化し、賃金については成果主義を導入して過労死を生み出してきた。そして、それまでの「1億総中流時代」の中間層を破壊して、生活保護世帯同様の所得の非正規労働者に大量に置換え、一部の高所得者と低所得者との格差社会を作り出してしまったのである。いまや雇用の安定など何処にもない。何時わが身が生活基盤を失うことになるか分からない時代になっている。 その上で、賃金については、「春季労使交渉・協議において、月例賃金を重視した賃金引上げの重要性が指摘されることが多い」として、連合の賃上げ要求に、「賃金底上げを図る市場横断的なベースアップはもはやありえない」と全面否定し、相変わらず「仕事・役割・貢献度を基軸にした賃金制度の構築・運用が重要」として海外についても拡げろとしている。 (3)政策・制度について 第4章の政策・制度については、「全員参加型社会構築」として、フリーター対策、学生の就業意識形成、産学官連携の教育、ハローワークの重点化、育児・介護支援、中小企業支援などを上げ、本来企業自らが行うべきことについては何も指摘せず、国・行政・社会全体の問題としている。その上で、労働者派遣法については「雇用の創出・確保と言う点において重要な機能をはたしている」とし、新たに外国人労働者については『日本型移民政策』として、受け入れへ向けた法制面・行政面の整備が必要として、使いがってのいい労働者を拡大しようとしている。 そして、最低賃金制度については見直せ、道州制については2015年までに行え、消費税の引き上げは避けて通れない、と都合のいい政策要求をしている。 3・まとめ 経営側は、昨年9月の「米国発の金融危機」としてこの不況を外的要因によるもので、「自分たちには責任が無い」としているが、この経済危機はこれまでの新自由主義による市場万能の経済運営とグローバル化の結果であり、経団連に参加している大企業・多国籍企業が押し進めたものである。その結果「希望の国日本」と大儲けをしてきた彼等こそ、その犯人であり、この責任を取らなければならない張本人である。 そして、昨年末から派遣・期間工切りなどで、年を越せない人々が多く発生して問題になった。しかし、従来から言われていた09年問題がある。06年に派遣法改正(改悪)され、雇用期間を1年から3年に延長されてそれ以上雇用する場合は正社員化することになった。企業は、その法施行を見込んで1年前から大量の派遣労働者を採用した。その期限が09年3月末となる。その上に、今回の金融危機を迎える。したがって、この春はこの年末を越える大量の失業者が発生する。このことが分かった上で、企業は昨年から雇用期間中の派遣切りを行っているのである。  経団連会長の御手洗冨士夫が序文で「企業は自社の売り上げや利益を追うだけでなく、社会や国、世界に貢献し、信頼を得ていかねばならない。経営者は経済社会に不可欠な『社会の公器』の運営を委ねられているとの自覚と、高い倫理観を持って経営に専念してゆく必要がある」と言っている。全くそのとおりだ。しかし、偽装請負問題を起こしたのも、大分キヤノンの派遣切りを行っているのも、キヤノン=御手洗であり、この序文を書いた本人が反省しなければならない。その上で金融カジノ経済を行ったが故のこの危機から逃れる為には、モノ経済=実体経済を再構築しなければならない。その需要を起こすのは労働者国民であり、不安な雇用の改善と賃上げによらなければ需要はおきない。しかも、今日の大量消費社会ではなく持続可能なグリーンエネルギーを目指したものでなければならない。その認識が、この報告書のどこにも見あたらない。 経団連会長の御手洗冨士夫が序文で「企業は自社の売り上げや利益を追うだけでなく、社会や国、世界に貢献し、信頼を得ていかねばならない。経営者は経済社会に不可欠な『社会の公器』の運営を委ねられているとの自覚と、高い倫理観を持って経営に専念してゆく必要がある」と言っている。全くそのとおりだ。しかし、偽装請負問題を起こしたのも、大分キヤノンの派遣切りを行っているのも、キヤノン=御手洗であり、この序文を書いた本人が反省しなければならない。その上で金融カジノ経済を行ったが故のこの危機から逃れる為には、モノ経済=実体経済を再構築しなければならない。その需要を起こすのは労働者国民であり、不安な雇用の改善と賃上げによらなければ需要はおきない。しかも、今日の大量消費社会ではなく持続可能なグリーンエネルギーを目指したものでなければならない。その認識が、この報告書のどこにも見あたらない。こうした経営側に対して、連合が09春闘で「雇用も」「賃上げも」と主張するのは正しい。しかし、それには彼らに口で言っても通じない、力が必要であり、私たちの闘いが求められている。 |
|||||||
| 6 | |||||||
|
|||||||
| はじめに 市場主義と自由競争を標榜して登場し世界中を席巻した新自由主義の破綻が明確になり、世界的に一大転換期を迎えている。 アメリカのサブプライムローン問題は一気に世界的な金融危機へと突入するとともに、世界各国の実体経済を直撃していまや世界は同時不況に陥っている。 1970年代以降実体経済で国際競争力を喪失し貿易赤字を拡大し続けたアメリカは、自らを「世界の金融センター」として形成することを通して世界経済のヘゲモニーを維持してきたが、その構造が崩壊したのである。アメリカにとってヘゲモニー維持の命綱といえるドル機軸通貨体制を根底から揺るがす事態となっており、アメリカへの一極集中から拡散する新たな経済秩序構築の模索が始まっている。新たな経済秩序を構築できなければ、戦争の危機が深まると指摘する学者もいる。 アメリカの世界経済のヘゲモニーの維持を支えたイデオロギーが新自由主義であり、それによる政策展開である。グローバル化に対応したアメリカンスタンダードの押し付けで、格差と二極化、貧困と差別の拡大に象徴される深刻な矛盾が世界中に広がった。新自由主義の特徴的な政策は、市場原理主義の下で規制緩和と民営化の推進、行政改革と小さな政府の推進にある。しかし、新自由主義の推進者たちは、他者には競争と自己責任を徹底して強制したが、自らは常にインサイダーとして情報を独り占めし、政財の徹底した癒着の下で談合を繰り返していた。今、際限のない金融危機が指摘されているが、債権の証券化はリスクの転売で責任の所在を不明確にさせ、経済システムが不安定になれば儲かる人が出るという不条理をもたらした。トランプゲームでは受け取るまいとするジョーカーが高値で売れるという転倒である。大きな政府を徹底して攻撃した張本人が、今回の金融危機では臆面もなく国家に助けを求め、巨額の公的資金が注入される。新自由主義は文字通り「人の不幸はわが身の幸福」路線であり、トリクルダウンの理屈も所詮は方便でしかない。まさに荒廃と腐敗は極まっており、今回の金融危機でその実態を世界中が実感した。カジノ資本主義とも言われた金融資本主義は、実体経済と乖離し人間の営みとは無縁のうちに肥大化して拡散したリスクが把握できないといわれている。構造的な危機である。 日本においても小泉構造改革に象徴されるように新自由主義的な改革が推し進められてきた。日本社会は、歪んだ富の分配構造、働く貧困層、そして蔓延する社会病理に特徴づけられるように、雇用・労働と所得、年金・医療・介護、教育、地域間、そして「生きる希望」という深刻な格差に覆われている。「派遣村」は象徴的である。 連合は2008年10月23日の中央執行委員会で、「『岐路』に立つ世界と日本・今こそパラダイム転換を/希望の国日本へ舵を切れ」との見解を明らかにした。「ウォール街の崩壊」はグローバルスタンダードと言われた市場原理主義の終焉を意味し、歴史的な転換点を迎える中でパラダイム転換が必要であり、連合は社会的責任と使命を果たす決意を示した。 連合は、09春季生活闘争方針で、消費者物価の上昇を受けて01年以来絶えていたベア要求を掲げた。「賃金も雇用も」との方針である。一方で、経営者は、金融危機と大不況に身構えて、とりわけ製造部門で「派遣切り」「期間工切り」を矢継ぎ早に行い、これからは正規労働者の解雇も射程に入れているといわれる。このような経営者の身勝手な振る舞いは断じて許されない。その結果ではあるが、多くの労働者が働く場を奪われ、住居にも事欠く生活を送っている事実がある。大切なことは、企業の理不尽な解雇攻撃を許さず、また働く場を奪われた労働者への支援など具体的な取り組みであり、これを抜きに09春闘の前進はあり得ない。ナショナルセンター連合の指導性と具体的な取り組みが「名ばかりナショナルセンター」を克服させて社会的な共感を呼び、パラダイムシフトの成功へ導く。 全水道は、春闘を「働く者の闘いの広場」と位置付けてこれまで春闘を闘ってきたが、その真価が問われる09春闘と言える。賃金・労働条件・権利の低下や破壊、ともに現場で働く臨時・非常勤の仲間の賃金・労働条件・権利、企業の身勝手な解雇攻撃への反撃と労働者の支援、など現場の事実に基づいて具体的な闘いに取り組むことが必要だ。新自由主義政策のもたらした様々な歪からの具体的な回復が課題であり、「公共の再生」の重要なテーマとして、今春闘においても水道・下水道・ガス事業の公営原則防衛の闘いが柱の一つとなる。そして、09春闘で新自由主義を終焉させる具体的な礎を築かなければならない。その意味で衆議院選挙は決定的に重要な政治決戦である。 Ⅰ・08秋季年末闘争の中間総括(略) Ⅱ・特徴的な情勢(略) Ⅲ・上部団体の春闘方針 1・連合2009春季生活闘争方針 連合は、米国発の金融・経済危機により春季生活闘争をめぐる環境が日増しに厳しさを増しているが、実質賃金の減少で労働者の実質生活の維持が困難となっていることから、労働組合は、物価上昇に見合った賃金引上げを行い、自律的な経済発展へ転換することが必要であり、このことが最大の景気対策であるとしている。 また、「歴史の転換点にあたって~希望の国日本へ舵を切れ~」に基づき、効率と競争最優先の価値観から公正と連帯を重んじる社会の実現をめざし、政策の転換を求めるとしている。 連合は、09春季生活闘争を景気の回復と生活防衛のための取り組みと位置づけて総力をあげて闘争を推進するとし、(1)賃金をはじめとする労働諸条件の改善と、格差の是正、底上げに向けた強力な展開 (2)共闘連絡会義を立ち上げて「社会的所得配分メカニズム」の機能強化 (3)非正規労働者の雇用問題にも留意しつつ、すべての労働者の雇用と生活安定に向けて取り組み推進 (4)政策・制度の取り組み強化(金融機関の貸し渋り対策、中低所得者層に対する所得税減税、非正規労働者や中小・下請労働者に対する対応)を基本に取り組みを推進するとしている。 (1)すべての組合が取り組むべき課題(ミニマム運動課題) (1) 賃金カーブ維持分を確保したうえで、消費者物価上昇に見合うベアに取り組む (2) パート労働者なども含めた全従業員を対象に、賃金をはじめとする待遇改善に取り組む (3) 賃金の底上げを図るため企業内最賃協定の締結と、その水準を引き上げる (4) 長すぎる労働時間を是正するため総実労働時間の短縮を図る (5) 時間外・休日労働の割増率の引き上げに取り組む (2)具体的な労働条件の要求と取り組み (1) 賃金改定の要求と取り組み 賃金改善(賃金引上げ)ついてはその考え方を、○ア賃金カーブ維持分を確保したうえで、物価上昇に見合うベアによって勤労者の実質生活を維持・確保することを基本に、マクロ経済の回復と内需拡大につながる労働側への成果配分の実現をめざす ○イ中小・下請労働者の格差是正、非正規労働者の処遇改善や正社員化に向けて産別指導のもと取り組みを展開する、としたうえで、賃金水準(絶対額)の重視、月例賃金最優先、連合「賃金水準」の策定による産業間格差の是正や中小組合の体系整備・格差是正等の推進、賃金改善の情報開示を進めるとしている。 (2) 中小・地場組合の賃金改善 賃金引き上げ要求については、賃金カーブ維持分に加え、物価上昇をベースアップに含めた生活維持分の確保に重点を置いた要求目安とする。 (3) パート労働者等の待遇改善 時間給の引き上げについては、「絶対額1、000円程度」「単組が取り組む地域ごとの水準については、構成組織は現状を踏まえ中期的に『連合リビングウェイジ都道府県別の水準』を上回るよう指導」「定昇込みの引き上げ額30円程度」のいずれかに取り組む。 組織拡大に向けた取り組みを進めるとともに、「昇給ルールの明確化」「一時金の支給」「正社員への転換のルールの明確化」など実情に応じて推進する。 また、非正規労働者の処遇改善のための社会的キャンペーンを実施する。 (3)その他の課題 (1) 最低賃金の取り組みでは、連合リビングウェイジの水準を目標に企業内最低賃金の協定化と水準の引き上げや、法定最低賃金の大幅引き上げをめざす。 (2) ワーク・ライフ・バランスの実現と労働時間の短縮の取り組みでは、所定労働時間の短縮や時間外労働の削減などで連合「中期時短方針」の目標の達成に努めるとともに、割増共闘の実現で「時間外50%、休日100%の割増率」達成に向けて運動を推進する。 (3) 格差是正・底上げの進め方については、適正取引の確立と公契約運動による公正労働基準の確保、「改正パートタイム労働法を職場にいかす取り組み指針」(08年3月)に基づく全従業員対象の処遇改善の取り組み、地域における格差是正の取り組み、男女間の賃金格差の是正に取り組む。 (4) ワークルールについては、労働関係法令の遵守の徹底、快適な職場づくり、労働時間管理の徹底、管理監督者の取り扱いの適正化、65歳までの雇用確保、改正均等法定着と両立支援の促進、裁判員休暇(有給)制度に関する労働協約の締結について取り組みを進める。 (4)政策制度の要求と取り組み (1) 景気・消費回復や生活防衛のための総合経済対策の効果的な実施に向け、税制改革、地域・中小企業活性化対策、物価対策、公正な企業間取引の実現に取り組む。 (2) 雇用・労働分野におけるセーフティネットの整備に向け、「日雇い派遣」の禁止など労働者保護の視点での派遣法改正、時間外労働の割増率引き上げ、障がい者の適切な処遇改善等に向けた障害者雇用促進法改正、非正規労働者の雇用確保・安定化の推進に取り組む。 (3) このほか、「両立支援法」の実現をめざした育児・介護休業法の改正、社会保障制度の機能強化、年金医療制度改革と介護報酬の引き上げ、公務員制度・公務労使関係の抜本改革と労働基本権の確立に取り組む。 (5)闘いの進め方 社会的に賃金水準の形成を図っていくため、将来的には共闘を目標にして共闘連絡会義を設置するなど闘争体制を構築し展開する。 2・公務労協2009春季生活闘争方針 公務労協は、今が歴史の転換点という認識の下で09春季生活闘争を、公務・公共サービスのあり方をはじめとする日本社会の将来を決する取り組みとして、(1)すべての公共サービス労働者の生活の維持・確保、賃金水準の改善と格差是正 (2)良質な公共サービスの実現に向け、そのあり方の構築 (3)公務員制度の抜本改革と公務における労使・労働関係の改革の推進 (4)これらの取り組みを通じて組織の強化・拡大を図ることを柱に、組織の総力を挙げた取り組みを展開する、としている。 (1)賃金改善、格差是正、ワーク・ライフ・バランスの実現と労働時間短縮の取り組み 公務労協は、連合の方針に基づく具体的な取り組みを推進する。特に各構成組織は、格差是正の取り組みについて、臨時・非常勤職員の処遇及び雇用の改善に係る要求提出を必ず行うこととする。 (2)公共サービス基本法制定の取り組み これまでの取り組みを踏まえ、第171通常国会における公共サービス基本法の制定に向けて、民主党による院内対応とそれに連携した院外におけるキャンペーン活動を設定し、連合と連携した取り組みを進める。 (3)政策制度要求の実現に向けた取り組み 「景気・消費回復、生活防衛のための総合経済対策の効果的な実施」や「公務員制度・公務労使関係の抜本改革と労働基本権の確立」など連合が提起する政策・制度課題について、諸行動への積極的な参加等の取り組みを進める。 (4)公務員制度改革と労働基本権確立の取り組み 第171通常国会における内閣人事局に係る法制上の措置について、非現業公務員の協約締結権付与を前提に、内閣人事局を労使関係において政府を代表する責任ある使用者としての組織とすることを求める。 非現業公務員の協約締結権の検討に対しては、労使関係制度検討委員会における今後の検討・議論の推移を踏まえ、具体化される諸課題への対応を図る。 また、公務・公共部門の団体交渉制度の在り方に関する研究会報告に基づき、「労使関係制度についての公務労協の考え方」を策定し、組織的な討議を行う。 引き続き連合との連携の下、ILO勧告を満たした労働基本権の確立と民主的公務員制度改革の実現を求め、具体的な対応については、別途、公務労協・公務員制度改革対策本部に提起する。 (5)地方分権改革・国の出先機関の見直し、独立行政法人改革への対応 地方分権推進委員会の第2次勧告に対し、(1)国と地方の役割分担の明確化と事務事業の精査を前提 (2)政府の責任において雇用と労働条件の確保 (3)十分な交渉・協議、合意の前提などを基本とした対策を図るとともに、分権改革対策委員会の対応等の充実や取り組みの強化・全体化を行う。 独立行政法人の整理合理化計画の具体化及び見直しに対しては、引き続き行革・雇用問題対策会議を中心として、取り組みを強化する。 (6)賃金・労働条件に関する課題と統一要求基準 (1) 雇用と賃金等の取り組みでは、○ア連合に結集し、すべての労働者の雇用と実質生活の確保、格差是正の実現に全力を挙げる ○イ総人件費削減に対する取り組みの強化と公務員給与の社会的合意再構築に全力を挙げる ○ウ賃金水準の改善の実現、を主要課題とする。 公務・公共部門の役割を認識し、雇用確保の取り組みや格差是正、底上げ、公契約条例などの取り組みを全力で進める。 公務労協の2009年の統一賃金要求基準については、民間組合の取り組みに連帯していく立場から、「公務員労働者の実質生活を維持・確保し、改善する給与引き上げを行うこと」とする。また、各構成組織は、必ず関係当局に非常勤職員等の処遇改善(金額を明示した賃金引き上げ要求)と雇用確保に関する要求を提出し交渉を行う。 (2) 労働時間等の取り組みでは、○ア年間総労働時間1800時間の実現 ○イ独法等の所定労働時間短縮の交渉促進や地方公務員の所定勤務時間短縮の早期実現 ○ウ政府に対して勤務時間管理と実効性ある超勤縮減策のとりまとめを求めるとともに労働基準法の改正に対応した超過勤務手当の割増率の引き上げと全額支給の実現を求める。 (3) このほか、○ア段階的定年延長を中心とした新たな高齢雇用施策確立に向けた取り組み ○イ男女平等実現に向けた取り組み ○ウ人事評価の本格実施をめぐる取り組みを進める。 (4) このような課題と考え方を踏まえて、総人件費削減と雇用確保、官民比較方法と賃金水準の改善等、非常勤職員の雇用確保と処遇の改善などについて「2009年賃金・労働条件等に関する統一要求基準」を設定して公務労協全体で取り組みを進める。 (7)具体的な取り組みの進め方 (1) 要求提出については、公務員連絡会は2月19日、国営関係部会は3月上旬までに提出することとする。 (2) 都道府県においては、地方連合会との連携などにより2月~4月の間に春季生活闘争の諸集会等と連携した「公共サービス基本法の制定を求める地方集会」を開催する。地方集会の取り組みの集約点とする中央集会を5月~6月を目途に開催する。 3・公務員連絡会2009年春季生活闘争方針 (1)基本的課題と考え方 公務員連絡会は09春季生活闘争について、(1)連合に結集し実質生活の維持・確保と格差是正の実現に全力 (2)良い社会を作る公共サービス確立キャンペーンとの一体的取り組み (3)総人件費削減に対する取り組みの強化と公務員給与の社会的合意再構築に全力 (4)賃金水準の改善などの重点要求課題の実現、の4点の基本的考え方に基づき取り組みを進めるとしている。 (2)賃金をめぐる課題と要求の考え方 (1) 政府に対しては引き続き「地域別民間給与の実態公表とそれに基づく俸給表水準見直しの検討」要請の撤回を求め、人事院に対しては労働基本権制約の代償機能として毅然として拒否し、社会的に公正な官民比較方法とするよう求める。 (2) 賃金要求については、連合の考え方を支持し、民間組合の取り組みに連帯していく立場の下、「民間の賃金実態を正確に把握し、公務員労働者の実質生活を維持し、改善する給与引き上げを行うこと」とし、実質生活の維持を最低とし、生活改善につながる給与引き上げをめざす。 (3) 住居手当については、総合的に改善を求めるとともに、自宅に係る手当の「廃止」については、国・地方の支給実態等を十分に踏まえ、慎重に検討し、十分な交渉・協議・合意に基づいて進めることを求める。 定年の段階的延長など新たな高齢雇用施策に関わる給与体系・水準の見直しにあたっては、公務員連絡会と十分交渉・協議し、慎重な検討作業を行うことを求める。 (3)非常勤職員等の処遇改善と雇用確保 (1) 各構成組織は、連合の格差解消の取り組みに積極的に参加する。また、必ず関係当局に対して非常勤職員に関わる要求(時間給の30円引き上げを明示、雇用確保)を提出して交渉するとともに、公務における最低賃金の引き上げや非常勤職員等の均等待遇原則の確立、公契約条例の制定等に真剣に取り組む。 (2) 政府・人事院に対して、08人事院報告に基づいて非常勤職員の実態把握を行い、任用の位置づけや雇用確保策について公務員連絡会が参加する検討の場を設置し、政府全体として取り組みの開始を求める。また、休暇等の改善についても具体的な要求を提出して交渉・協議を行う。 (4)その他の課題と要求の考え方 労働時間に関しては、地方公務員の所定勤務時間短縮の早期実現、超過勤務縮減、労働基準法の改正もふまえた超過勤務の割増率の引き上げと全額支給の実現などに取り組む。 このほか、女性国家公務員の採用・登用拡大に関する指針の着実な実施など男女平等の課題、4月1日から本格実施が予定される評価制度の納得性や円滑な実施に向けた最終的な取組み、段階的定年延長を中心とした新たな高齢雇用施策の確立に向けた取り組みを進める。 また、公務員制度改革については、連合、公務労協に結集することを基本に取り組みを進める。現在、労働基本権制約下での勤務条件に関する企画・立案機能の内閣人事局への移管や給与制度見直しが検討されているが、代償機能の空洞化につながるだけではなく、憲法違反でもあることから、09春季の中心的な取り組みとして検討の中止を求めて政府との交渉・協議を強める。また、労使関係制度検討委員会においては公務の労使関係の抜本改革と団体交渉に基づく賃金・労働条件決定制度の構築に向けて取り組みを進める。 (5)取り組みの進め方 方針決定 :1月27日(火) 代表者会議にて方針決定 要求提出 :2月19日(木)(公務員連絡会、地公部会)春季要求書を政府、人事院に提出 交渉配置 :3月5日(木)幹事クラス交渉 3月13日(金)書記長クラス交渉 全国統一行動:第1次 2月20日(金)要求提出の翌日 第2次 3月13日(金)中央行動に連動 第3次 3月24日(火)回答指定日の翌日 中央行動 :3月13日(金)に1、000人規模の中央行動を予定 回答指定日 :3月23日(月)総務大臣、人事院総裁との委員長クラス交渉 その他 :要求提出日から3月下旬の間に、春闘課題と公共サービスキャンペーンの課題等を結合させ、地方公務労協、連合官公部門連絡会規模での決起集会を追求。連合の春季生活闘争関連諸行動・公務労協の諸行動に参加するとともに、公務労協・国営関係部会の取り組みを全面的に支援。また、連合の中小、地域民間の闘いに中央・地方レベルで支援・連帯する。 4・地方公務員部会の09春季生活闘争方針 地方公務員部会は、地方公務員に公務員の総人件費削減の焦点が当てられ給与決定構造や水準に具体的な攻撃が加えられていること、景気後退局面で地方財政は一層厳しくなる状況にあること、地方公務員の賃金闘争を早期に立ち上げる必要があることなどから、要求提出をはじめとした09春闘期の闘いを公務員連絡会と連携を深めて取り組みを進めるとしている。 (1)重点課題について (1) 地方公務員の実質生活を維持し、改善する給与引き上げ (2) 臨時・非常勤職員の均等待遇原則による雇用・労働条件の改善、公契約条例の制定 (3) 総務省「技能労務職員の給与の基本的在り方に関する研究会」最終報告に対する取り組み (4) 総務省「地方公共団体における人事評価の活用等に関する研究会」最終報告に対する取り組み (5) 民主的な地方公務員制度改革の取り組み (6) 09年度予算案、2010年度予算編成に向けた中央・地方段階での取り組み (2)取り組みの進め方 (1) 2月10日(火)には全人連に、2月19日(木)には総務省に対して、地方公務員の課題を中心とした要求書を提出する。回答指定日に向けて交渉を継続的に積み上げる。 (2) 各構成組織は、中央・地方段階でできるだけ速やかに(2月中)関係当局に要求書を提出し、春闘全体の取り組み課題と構成組織ごとの独自課題の解決に向けた取り組みを強める。 (3) 特別交付税削減、公的資金補償金免除繰上償還、退職手当債起債に関し、総人件費削減を強要させないよう中央の交渉や地方段階で取り組みを進める。 (4) 地方公務員の標準的給与の確立に向けた中長期的な展望に立って、諸条件を整備するため、総務省公務員部、全人連等との意見交換、協議を進める。地方の各共闘においても対応する人事委員会との意見交換を進める。 (5) 公務員連絡会の回答指定日である3月23日(月)に総務大臣交渉を実施する。また、4月に全人連から基本的見解を回答させるよう取り組む。 (6) 公務労協や公務員連絡会の取り組みを積極的に進めるとともに、連合の中小労働者の闘いにも中央・地方を通じて支援・連帯の取り組みを進める。 Ⅳ・09春闘における全水道の基調 金融危機とそれによる世界同時不況により新自由主義の破綻は明らかになり、世界は一大転換期にある。破綻した新自由主義を終焉させ、パラダイムシフト=安全、安心な「ともに生きる社会」の構築を進めなければならない。 一方、新自由主義は中間層を解体し、労働者に多大な犠牲を強いてきた。その爪痕は、労働組合に組織される正規雇用労働者より非正規労働者に著しい。労働者間の分断を克服し、ともに働き生きるためには、労働組合が社会的労働運動をこの春闘で実践することがまず求められる。組合員の賃金や労働条件はもとより、それにとどまることなく労働者全体の利害を掲げて闘わなければならない。春闘における総労働の闘いによってこそ、労働者の分断克服の道が開かれ、公務員賃金の社会的合意の再構築や公務員労働者の労働基本権回復の闘いも前進する。 全水道が掲げる「働く者の闘いの広場」たる春闘が改めて問われており、全水道は次のような基調の下で09春闘を闘う。 (1)経団連「経労委報告」に対決し、春闘の再構築で、すべての労働者の雇用と生活できる賃金の獲得を 経団連を中心とした経営側は、「雇用か賃金か」ではなく「雇用も賃金も要求には応じられない」という態度を明らかにしている。一方連合は、「雇用を守り賃金引き上げも」要求して闘いを進める。 今春闘では、すべての労働者の雇用と生活できる賃金の獲得をめざさなければならない。そのためには、本工主義に埋没せず、企業内労使関係に収斂させない、要求と闘いが不可欠である。 全水道は、公務員労働者の一体となった闘いの推進の中で春闘期において具体的な賃金回答を引き出すことが困難な状況にあるが、水道・下水道・ガス事業に働くすべての労働者の雇用と生活できる賃金の獲得をめざして要求し闘いを進める。この取り組みを通じて、官民分断や正規・非正規の分断を克服する努力を行い、総労働と総資本の対決としての春闘の実現に向けて奮闘する。 (2)分断を許さず、社会的要求の前進を 労働者間の分断を克服し、ともに前進するためには、社会的要求を掲げて前進を図ることが求められる。全水道産別内においては、臨時・非常勤職員等の雇用を守る闘いをはじめ均等待遇原則による格差是正の取り組みを進めるとともに、公契約条例の制定に向けて取り組みを強化する。 また、社会問題化している企業による派遣労働者や期間工の解雇を許さぬ闘いを連合非正規労働センターや非正規雇用フォーラムに結集して推進する。 連合が提起するミニマム運動課題を産別内の意思統一の下で単組から取り組むとともに、公務労協や公務員連絡会の公務内における格差解消に向けた統一要求基準を踏まえて春季産別統一要求に反映して前進をめざす。 (3)公務公共サービスの解体・縮小を許さず、水道・下水道・ガス事業の公営原則の防衛を 民営化や小さな政府を推進してきた新自由主義の破綻は明確になったが、日本では、公務・公共サービスの解体攻撃は依然継続されている。むしろ、水道・下水道・ガス事業においては、民営化や業務委託の拡大攻撃が、関連産業界の要請もあって強まっている。産業界のための事業か、住民・市民のための事業か、岐路にあるといっても過言ではない。 全水道は、09春闘においても、水道・下水道・ガス事業の民営化と業務委託の拡大を許さず、事業の公共性と事業基盤の防衛に向けて政策闘争と反合闘争を結合して闘いを進める。09春季産別統一要求の一つの柱である政策に関する基本要求に、技術基盤確立のための人員確保に向けた要求を掲げ、全単組で取り組みを進める。 あわせて、PSIが提唱する、民営化に反対し質の高い公共サービスの実現をめざす「水行動プログラム」を、3・22国連世界水の日を中心に取り組みを進める。また、3月の第5回世界水フォーラムには、水関連事業の私企業化に反対して、PSIやNGOの仲間と連携した取り組みを進める。 このような闘いを通じて、公務労協が進める公共サービス基本法制定の取り組みを積極的に進める。 (4)公務員制度改革・労働基本権回復をはじめとした公務部門の課題の前進を 公務部門をめぐっては総人件費削減と地方分権改革、公務員給与の新たな体系と水準見直しの動き、無年金時代を迎える中での新たな高齢雇用制度の創出、公務員制度改革と労働基本権の回復など課題が山積している。 なかでも、公務員制度改革と労働基本権回復は、統治機構の再編とかかわって展開されていることから、労働基本権制約下での勤務条件の企画・立案機能の内閣人事局への一元化や給与制度見直しの検討など、憲法違反の攻撃と対決しなければならない状況を迎えている。全水道は、公共の再生とそれを通じた安全・安心の「共に生きる社会」を担う民主的な公務員制度の確立と公務員労働者の権利と地位の向上を図る労働基本権の回復に向けて、連合、公務労協に結集して取り組みを進める。 (5)新自由主義を終焉させ、政策転換を 08年度第2次補正予算案、09年度予算案をめぐって国会は流動的であるが、いつ解散・総選挙が実施されても不思議はない状況にある。 破綻は明確になったが、人々を決して幸せにすることはない新自由主義を終焉させなければならない。この意味において来るべき衆議院選挙・政治決戦は決定的に重要である。新自由主義の延命と保守二大政党制への収斂を許さぬ立場から、全水道は09春闘を政治決戦の臨場感をもって取り組みを進める。 (6)09春闘を真に「働く者の闘いの広場」として推進を 全水道は09春闘を引き続き「働く者の闘いの広場」として位置付けて職場・地域から積極的に取り組みを進め、労働組合としての社会的責任を果たすよう努力する。 時代の一大転換点を迎える中で、「働く者の闘いの広場」という合言葉は輝きを増している。同時に、個別利害にとどまらない社会的労働運動の真の推進を待ったなしにつきつけている。企業の社会支配を許さずすべての労働者の雇用と生活できる賃金の獲得、公共サービス基本法の制定と地域公共サービスの確立、労働基本権の回復、不公平税制の是正と社会保障制度の再構築、護憲・反戦平和・脱原発、反差別人権確立をはじめ、総選挙闘争勝利の体制を構築し、安全・安心な「共に生きる社会」を展望する春闘として全力を挙げる。 Ⅴ・具体的な闘いの課題と取り組み 1・未解決課題への取り組み 08秋季産別労働条件統一闘争については、中間総括で明らかなように、前進ある回答の引き出しが難しい局面にあることや、業務の民間委託をはじめとした当局側の攻撃などにより、未解決の単組が多く見られる。 このような状況を受けて、昨年12月22日の第3回戦術委員会では、08秋季産別労働条件統一闘争を継続し前進を図ることとした。このようなことから、未解決の単組では09春闘前段の闘いと位置づけて引き続き労使交渉を実施し、要求の前進と攻撃への反撃を期すこととする。それにおいてもなお未解決の場合は、09春季産別統一要求に連続して取り組みを進めることとする。 賃金制度や賃金水準の改悪・引下げ、事業の公共性や事業基盤を損なうような業務の民間委託攻撃や大規模な人員削減合理化、人事評価制度の導入が交渉の焦点となっている単組については、十分な交渉・協議と合意を前提に一方的な改悪・実施を許さぬよう、組合員との意志統一を図って闘いを推進することとする。 2・賃金要求をはじめとした09春季産別統一要求 (1)賃金要求の考え方について 全水道は09春闘と賃金闘争の基礎資料を得るために、公務員連絡会の生活実態調査に並行してアンケートを実施している。 「賃金収入とその評価」では「満足」が微増し「不満」が微減しているが、「昨年の今頃と比べた生活」では、「苦しくなった」は59・1%で昨年を上回る一方「楽になった」は2・4%と昨年を下回り、生活の逼迫感は強まっている。 「ゆとりある生活の実現」に関する調査結果では、「ゆとりある生活のための必要な手取り賃金」が昨年に比べ△3・1万円で控え目な「必要手取り額」となり、「手取り賃金」と「ゆとりある生活のための必要な手取り賃金」の差は、△7・5万円(昨年は△8・9万円)で減少した。 公務員連絡会は、09春季生活闘争の賃金要求については、「物価上昇に見合うベアと労働側への成果配分の実現」という連合方針を支持し、民間組合の取り組みに連帯していく立場から、「民間の賃金実態を正確に把握し、公務員労働者の実質生活を維持、改善する給与引き上げを行うこと」とした。また、公務内の均等待遇原則による格差解消をめざして、「構成組織は、必ず関係当局に対して非常勤職員に関わる要求(30円の有額要求、雇用確保)」を内容とする統一要求基準を策定した。 全水道においては、昨08春闘の賃金要求に関して「産別統一の有額要求が必要ではないか」との要望を受けて、今09春闘の賃金要求の在り方について検討を加えてきた。かつて全水道は、公務員共闘(公務員連絡会の前身)時代に有額要求を行ってきた経過にあり、公務員連絡会の要求協議においても有額要求の必要性や相場形成への参加など春闘期の闘いも重視した取り組みを求めてきた。一方全水道産別内では、組合員参加の下で賃金要求アンケートを実施するなど独自の取り組みを継続し有額要求を行っている地本・県支部・単組も存在する。このような現状を考慮して、今09春闘において全水道は、有額要求は組合員の切実な要求に基づく賃金要求とその闘いの推進にとって大切ではあるが、賃金アンケートをはじめ産別内の十分な取り組みを実現するまでには至っていないこと、統一要求による統一闘争の推進の立場から公務員連絡会や地公部会に結集して春闘期から人勧期・確定期を闘い抜く必要があること、などから、09春闘の賃金要求については、公務員連絡会や地公部会の提起を受け止めて、要求作りを行う。 地本・県支部・単組においては、これまでの賃金要求の在り方をふまえて要求を付加して前進を図ることとする。なお、産別内の格差解消に向けた取り組みについては、公務員連絡会などの統一要求基準などを踏まえて、有額回答を勝ち取るべく取り組みを強化する。 (2)09春季産別統一要求 諸要求実現に向けて、09春闘においても「賃金・諸手当に関する要求」「臨時・非常勤等職員の賃金・労働条件に関する要求」「ワーク・ライフ・バランスや男女平等・共同参画の実現に向けた要求」「公営原則など政策課題に関する要求」を柱に09春季産別統一要求書を作成し前進を図る。 要求内容については、戦術委員会や賃金専門委員会の検討を踏まえて、第124回中央委員会で決定する。要求書は本部統一要求に地本・県支部・単組要求を付加して提出することとする。 なお、要求策定にあたっては、臨時・非常勤等職員の格差解消に向けた取り組みや民間部会関連単組と労働者の要求の前進が、雇用の防衛を含めて待ったなしで求められていること、また、事業の公営原則の防衛には技術基盤の確立が不可欠でそれを支える職員配置の獲得が重要性を帯びていることを勘案することとする。 また、課題となっている、産別統一要求の全単組での推進については、春闘期を出発点に秋季闘争での決着をも展望して、戦術委員会で協議し取り組みの強化をめざす。 3・公務部門に関わる課題と闘い 公務部門に関わる課題については、公務労協、公務員連絡会に結集して前進を図ることを基本に取り組みを進める。 なかでも、労働基本権問題については、今春闘において、労働基本権制約下での使用者権限の拡大という憲法違反の攻撃を跳ね返すことが重要な課題となっている。また、非現業公務員の協約締結権回復に向けて理念と制度設計を公務労協・団交研究会で行い報告をまとめることとなっていることから、現行の権利が後退することのないよう積極的に対応を進める。 4・水道・下水道・ガス事業に関わる課題と闘い 新自由主義政策の破たんは明らかになったが日本では公共サービスの解体攻撃、民間開放の攻撃が継続されている。生活に欠くことのできない水道・下水道・ガス事業の公営原則と事業基盤の防衛・確立、それに伴う業務と労働条件の確立に向けて、09春闘期に次のように取り組みを進める。 (1) 水道・下水道の水関連事業については、民営化反対と質の高い公共サービスの実現をめざすPSIのQPSキャンペーン(質の高い公共サービスキャンペーン)の一環として「水行動プログラム」を、3・22国連世界水の日を中心に取り組む。また、3月の第5回世界水フォーラムに代表を派遣し、水関連事業の私企業化に反対する取り組みを進める。 (2) 単組においても、春季産別統一要求の事業政策に関する基本的要求について前進ある回答を求めて交渉を展開し、公営原則と事業基盤の防衛・確立、それに伴う業務と労働条件の確立に努力することとする。とりわけ技術基盤の確立に向けて今春闘を出発点に取り組みを強化する。 (3) 国際貢献と国内市場、水道・下水道事業の再編・構築など水問題をめぐる政治や業界の動きは活発化している。 全水道は、引き続き水基本法の制定を柱に、総合的な水政策の確立と推進、水道・下水道事業の公営・公共原則の防衛、公公連携を基本にした事業の再構築、国際貢献を求め政治対策を含め内外での取り組みを強化するよう努める。 (4) 公営ガス事業については、長岡市において民営化の動きがあり、ガス政策中央対策会議と連携して取り組みを進めている。また、柏崎市については中越沖地震被害の復旧を優先してきたが、再度民営化に向けた動きがみられる。 本部は、引き続きガス政策中央対策会議で協議し闘争体制を確立するとともに、闘争を通じて、当該単組、地本そして産別全水道の組織強化が図られるよう取り組みを進める。 5・当面する春季政治課題と取り組みについて (1)春季政治闘争課題については、当面する主要な反戦・平和闘争課題とまじかに迫った衆議院解散・総選挙闘争を中心とした総合的な取り組みを強化していくこととする。 i 憲法改悪反対!反動諸立法を許さない取り組み 参議院の与野党逆転により「改憲策動」は、大きく後退したといえる。しかし強行採決された「改憲手続法」では、衆参両院に憲法審査会を設置することとなっており、立憲主義に基づいた「審議のやり直し」と「改憲策動」を許さない取り組みが重要となっている。加えて「なし崩し改憲」「解釈改憲」に対する取り組みが極めて重要となっている。そのためにも衆議院総選挙での政権交代を見据えながら引き続き取り組みを強化していく。 具体的には、以下の取り組みを中心に運動を進める。 (1) 1月31日から四国・高松で開催される第45回護憲大会(1月開催)への積極的な参加と大会の成功を目指す。 (2) 「武力で平和はつくれない!9条キャンペーン」の取り組みや国会対策などを進め、「憲法改悪」反対の取り組みを反戦・平和闘争と結合させた取り組みを強化する。 ii 自衛隊の海外派兵と戦争のできる国づくりに反対し、国際的な反戦運動の連携を強化する取り組み 新テロ特措法は本年1月15日にその効力が失効することから、麻生内閣は昨年国会の会期末を延長してまで改正新テロ特措法を採決した。従って自衛隊の戦地派兵と米軍支援を許さぬ取り組みを引き続き強化する。 また、昨年11月、田母神元航空幕僚長の懸賞論文問題は、自衛隊幹部教育の中で歪んだ歴史教育が行われていたことを明らかにした。しかもそれを歴代政府がチェックできていなかったことは、憲法の根底を揺るがす大問題であり、決して容認できるものではない。自衛隊の軍としての強化を許さぬ取り組みを進める。 iii 在日米軍基地の再編・強化、原子力空母横須賀母港化に反対し、全国的な反戦・反基地闘争を強化する取り組み 在日米軍再編は、完了期限の2014年に向けて実質的な作業が進められている。 しかし一方で、米艦船をめぐる深刻な事故が連続して露見し、新たな社会不安を発生させている。また、米原子力潜水艦による初入港や無通告寄港など米海軍の行動が目立ち、米合同演習も11月以降において、滋賀県、九州沖合、朝霞駐屯地などで行われ、同米軍基地や自衛隊基地を抱える地域で様々な立場からの抗議や反対行動が展開されており、引き続き連携する取り組みが重要となっている。 全水道は当面、以下の取り組みを中心として、各地で取り組まれる反戦・反基地闘争や総合的な反戦・平和の取り組みを強化させてゆく。 (1) 「平和フォーラム全国活動者集会」「ビキニ・デー集会」(3月2日、3日)に参加し広範な人々と共に反戦・反基地闘争を取り組んでいく。 (2) 「沖縄平和行進」(5月14日~17日)については、青年女性部の全国動員を中心として全水道基本組織の代表動員も取り組み、沖縄と全国を貫いた反戦・反基地闘争を強化していく。 iv 日朝国交正常化をはじめとする東北アジアの非核・平和確立の取り組み 12月8日に6カ国協議首席代表者会合が北京で約5か月ぶりに再開され、朝鮮半島の非核化に向けたプロセスは、核の検証と廃棄という第3段階におけるもっとも重要かつ困難な作業へと進むように、6カ国が誠実に取り組むことが求められている。 全水道は、その一連の動向を踏まえ「日朝ピョンヤン宣言」などで確認された原則をもとに、日朝国交正常化、東北アジアの平和確立に向けた取り組みを強化するとともに、全国各地の取り組みに参加し連携を強化してゆく。さらに戦後補償に関わる支援などを取り組み、他民族・多文化共生の社会を築く取り組みを強化する。 v 狭山差別裁判糾弾・再審要求闘争、人権確立の闘い、国鉄闘争をはじめとする様々な共同闘争を前進させる取り組み 昨年12月10日、世界人権宣言が国連で採択されてから60年を迎え、世界は、この間30にも及ぶ国際人権条約を積み上げてきた。しかし、日本は、人権救済に関する水準は世界から大きく遅れており、「差別は社会悪であり、犯罪である」という姿勢を明確にした取り組みが極めて重要になっている。 具体的には、引き続き部落解放共闘に結集し「狭山差別裁判糾弾・再審要求闘争」を闘う。さらに、人権侵害救済に関する法律制定を目指す取り組みを強化する。加えて、平和フォーラムに結集し、「JR採用差別問題」など重要な段階・局面を迎える取り組みをはじめ、様々な共同闘争を引き続き前進させてゆく。 vi 反核・脱原発の取り組み 米印原子力協力協定を受けて、インドへの原子力関連輸出を例外として認められたことは、隣国パキスタンや北朝鮮、核開発疑惑のあるイランやイスラエルに対して核保有の口実を与えたことになり、NPT(核拡散防止条約)体制の形骸化・崩壊を招きかねない事態が進行している。停滞している核軍縮の流れを軌道修正する様々な取り組みを強化し、以下の取り組みに積極的に参加してゆくこととする。 具体的には、「原水爆禁止世界大会・広島大会、長崎大会」、「六か所再処理工場稼働阻止行動」、「もんじゅ運転再開阻止!全国集会」など全国各地・中央の脱原発運動の取り組みを強化し、広範な人々との共同行動を推進する。 (2)第45回衆議院選挙闘争方針 i 基本的な対応方針 全水道は、選挙闘争方針基調を「社民・民主・リベラル勢力の総結集を目指す政党との協力・支援関係を強化する」と整理し、具体的には社民党・民主党を中心としたリベラル勢力の勝利を目指し奮闘してきた。 したがって先の第62回定期全国大会において確認した「政治活動の基本姿勢」「当面する政治闘争(選挙闘争)を強化する取り組み」、さらには第123回中央委員会確認の「第45回衆議院選挙闘争方針」を基本として、当面する国会情勢を注視しつつ衆議院解散総選挙へ向けた具体的な対応を推進していくこととする。 (1) 自公連立政権に対する全水道の基本的態度について 麻生首相の政治姿勢は、所信表明などから見ると、構造改革よりも景気対策を優先するとしてきたが、それぞれの局面で矛盾に満ちた方針を示している。国際的な金融危機にも有効な手立てを講ずることができず、緊急経済対策も国民生活の不安を解消するに至っていない。麻生自公連立政権はすでに政権担当能力を喪失している。私達は、新自由主義政策を終焉させ安全・安心な「ともに生きる社会」の実現に向け、政権交代を実現しなければならない。 従って、政治闘争基調と基本的態度を堅持して、予定される衆議院解散・総選挙に対応しうる組織的準備を整え、様々な大衆運動の力を総結集し与野党逆転・働く者の新たな政権の確立を目指して奮闘する。 (2) 衆議院解散・第45回衆議院選挙闘争への対応について この間全水道は自公連立政権の打倒と野党共闘による新たな政権の確立に向け取り組みを強化することを確認してきた。現状において衆議院解散・総選挙の時期を予測するのは困難となっており、引き続き組織的準備を進めていくこととする。 そのため本部段階では、協力・支援関係にある政党との間で情報交換・協議などを進め、衆議院解散・総選挙の実施時期が確定される段階で、別途具体的対応を提起する。 ii その他の選挙闘争への対応について 直面する行革・規制緩和攻撃、市町村合併後の種々の課題、広域化問題など、地方自治体・地方議会をめぐる諸課題への対応強化が重要になっている。また、4月に行われる東京都議選をはじめ各地の自治体選挙については、全水道議員連盟に所属する各議員と出身単組・県支部・地本が連携した総合的な取り組みを強化する。 Ⅶ・09春闘の具体的な進め方、戦術について 1・闘いの推進構造 春闘基調で全水道は、破綻した新自由主義を終焉させてパラダイム転換を図る、社会的労働運動を進めて賃金・労働条件はもとより労働者全体の利害を掲げて闘う、など社会的責任を果たすための決意を示した。 全水道は09春闘において、連合方針に基づく民間組合の闘いへの支援連帯による相場形成やミニマム運動課題の推進で官民一体の闘いの追求、公務労協・公務員連絡会・地公部会とともに地域公共サービスの再確立や統一要求基準による賃金・労働条件の前進、春季産別統一要求による臨時・非常勤等職員や民間部会関連労組を含めた賃金・労働条件の改善をめざして闘いを進める。また、金融危機と大不況に身勝手な企業防衛を振りかざし、理不尽にも派遣労働者や期間工をはじめとした労働者の解雇攻撃が激化する事態に対して、労働者保護に向けた派遣法の抜本改正の取り組みや支援・連帯に取り組む。 全水道はこれら春闘期の要求や課題の前進に向けて次のような構造で「働く者の闘いの広場」としての09春闘を推進する。 (1) 連合の闘いの前進をめざし、中小共闘やパート共闘の取り組みに引き続き連携を深めるとともに、新たに設置された共闘連絡会議については地域公共連合を通じて「インフラ・公益共闘連絡会議」に結集する。また、中央・地方で諸行動に積極的に参加する。 (2) 公務労協・公務員連絡会・地公部会と連携を深め、統一要求・統一闘争を推進する。また、中央・地方で諸行動に積極的に参加する。 (3) 09春季産別統一要求を全単組で取り組み、諸要求の前進をめざす。産別内での均等待遇と格差解消が重要な課題であり、雇用問題を含めて臨時・非常勤等職員の格差解消に向けた取り組みや民間部会関連労組・労働者の要求前進に取り組む。臨時・非常勤等労働者に関する要求については組織化の努力と合わせて取り組みを進める。また、民間部会関連要求については、局組合や地方本部の支援や協力が不可欠であり、要求作りの主体的な論議を尊重しつつ、要求掘り起こしから取り組みまで局組合が積極的に関わるとともに、地方本部の強力な指導性の発揮に留意して取り組みを進める。 (4) 全水道は労働2権を有する労働組合として団体交渉を進め、合意内容を労働協約として締結する。闘いの戦術については、ストライキを最高戦術に設定し、多様な戦術を駆使しながら闘いを進める。このため、年間を通じた2時間ストライキ2波のストライキ権批准に向けて一票投票を実施する。 (5) 金融危機と大不況を背景に、労働者の解雇攻撃も激化することが予想される。全水道は、従来通り地区労からの争議支援要請などについても共闘の実績を踏まえつつ、積極的に参加する。また、企業の身勝手な派遣労働者や期間工などの解雇攻撃に対して、連合非正規労働センターや非正規雇用フォーラムと連携して取り組みを進める。 2・要求提出について 公務員連絡会は、2月19日(木)に対政府・人事院に春季要求書を提出し、09春季の闘いを本格的にスタートさせ、3月23日(月)の回答指定日に向けて全力で取り組みを進める。 全水道は、2月18日(水)に開催される第124回中央委員会の方針決定を受けて09春闘の本格的なスタートを切ることとなる。各単組においては、単組要求などを付加した09春季産別統一要求書を中央委員会終了後から速やかに当局に提出して春季の単組交渉をスタートさせる。春季産別統一要求の回答指定日については、公務員連絡会の回答指定日である3月23日(月)をめどに設定し、前進ある回答をめざして総力を挙げることとする。 3・春闘の山場と行動日程 全水道は、公務員連絡会の春季要求と全水道産別統一要求の回答指定日である3月23日(月)を最大の山場に設定して闘いを推進する。 具体的な行動日程は次の通りであり、中央段階における諸行動には例年通り関東地本の協力を得ながら参加することとする。なお、09春闘勝利をめざした全水道の中央総決起集会は全国動員体制で取り組むこととし、公務員連絡会の書記長クラス交渉と中央行動が取り組まれる3月13日(金)に開催することを予定し、具体的には別途指示することとする。 〔当面の行動日程〕 1月23・24日 全水道09春闘討論集会 1月27日 公務労協・公務員連絡会・地方公務員部会 代表者会議 2月10日 2009春季生活闘争・闘争開始宣言中央集会 2月10日 地方公務員部会 全人連要請 2月10日~ 連合・非正規労働者の処遇改善ための社会的キャンペーン期間 3月7日 2月18日 全水道第124回中央委員会 2月19日 公務員連絡会・地方公務員部会春季要求書提出 2月19日~ 全水道09春季産別統一要求提出 2月20日 公務員連絡会・第1次全国統一行動 2月下旬~ 連合・パート労働者の集い 3月上旬 3月2日~ ストライキ権批准一票投票 6日 3月4日 連合・国際女性デ―全国行動、中央集会 3月5日 公務員連絡会・幹事クラス交渉 3月7日 連合・2009春季生活闘争・政策制度実現中央集会 3月10日 ストライキ権批准一票投票結果本部集約 3月13日 公務員連絡会 書記長クラス交渉、第2次全国統一行動、中央行動 09春闘勝利!全水道中央総決起集会(予定) 3月16日~ 連合 第1の山場(最大の山場:3月17日~19日) 19日 3月22日 国連世界水の日行動 3月23日 公務員連絡会・地方公務員部会回答指定日(委員長クラス交渉) 3月23日~ 連合 第2の山場 28日 3月24日 公務員連絡会第3次全国統一行動 3月31日 連合・中小・パート共闘情勢報告交流会 3月30日~ 連合 第1次解決促進ゾーン 4月4日 4月13日~ 連合 第2次解決促進ゾーン 18日 4・ストライキ戦術の取扱いと一票投票の実施 公務の人勧グループにおいては制度的制約から春闘段階において有額回答を勝ち取ることが困難な現状にあるが、全水道は、官民一体となった総力を挙げた闘いを追求して賃金相場の形成をはじめ、脱格差社会の構築、公共サービス基本法の制定や公務公共サービスの確立など全労働者にかかわる社会的要求の前進をめざす。 また、公務部門は厳しい情勢の下で多くの課題を抱えているが、公務部門における均等待遇の実現、労働基本権の回復、公務公共サービスの再確立と雇用・労働条件の確保など重要な課題の前進をめざして取り組みを推進しなければならない。 産別内においても、春季産別統一要求の前進を図ることはもとより、賃金制度改悪や賃金削減、事業の存在意義と基盤を損なうような厳しい大合理化攻撃との対決など、通年的な闘いを迫られる状況にもあり、全水道全体の取り組みとする必要も考えられる。 連合をはじめ公務労協、公務員連絡会、地方公務員部会においては統一ストライキ戦術は設定されてはいないものの、全水道の全国的統一と団結の下で総力を挙げて闘いを推進する体制を構築する必要があることから、春の段階において、年間を通じて2時間ストライキ2波の戦術について一票投票を実施する。闘いの決意を示し、組合員の統一と団結の下で闘いを推進する体制構築に向けて、全単組においてストライキ権批准一票投票を成功させ、高率で批准するよう要請する。 一票投票については、各単組において3月2日(月)から6日(金)のゾーンで実施し、地本集約を経て3月10日(火)までに本部集約することとする。 |
|||||||
| 7 | |||||||
|
|||||||
| 公務員連絡会は2008年10月~11月にかけて、09春闘・賃金闘争の基礎資料を得るため「生活実態調査」を実施した。全水道の集約数は107単組・3614人。09年「連合白書」は「生活主導型経済へのパラダイムシフト―効率と競争最優先から公正と連帯を重んじる社会へ」を表題としたが、07年2月にEU社会党は新自由主義に対し社会連帯のあり方を換える政策を発表、その中心課題は「仕事を中心とした福祉社会」である。教育訓練を最重視し人的資本への投資を通じて万人に“いい仕事”、技能が向上し賃金が上昇しそして生活とのバランスがとれるディーセント・ワークの提供を構想しているという(「福祉ガバナンス宣言」連合総研編/07年11月)。今回の調査結果からは、全水道組合員が賃金水準の停滞・低下と人員削減や公務員バッシングに対しても、職場の仲間そして仕事へのやりがいに、なお多くの〈満足〉を示したことに留意したい。そのことが「転換点」から新たな方向を駆動する「連帯と相互の支え合い」の基軸となるのではないか。今回は、賃金収入の状況や、昨年と比べた生活、さらに現下の格差社会に公共部門で働く全水道組合員の仕事や職場の現状・将来への問題意識など、生活諸側面の評価や考え方をみてみる。 調査の属性 (1)性別・年齢・勤続・役員経験―男性89・2%:女性10・4%、年齢中央値で同40・5歳、34・5歳、総計で39・5歳(3)勤続中央値同17・5年、14・5年、17・5年 (2)労働組合の役員経験の有無―総計では「現在役員をしている」28・7%、「過去にした」24・6%、「したことはない」47・8%。回答者の過半数が役員を経験。男性で「現在役員」が28・2%、女性14・6%。「過去にした」男性は28・2%・女性23・1%、「したことはない」男性46・4%・女性61・2%。 (3)住居状況―住居の状況は、「持ち家ローン返済中」が総計45・8%・男性46・9%・女性37・2%。「民間の賃貸住宅」は同18・9%・18・6%・22・1%。「持ち家ローン返済なし」同10・6%・10・9%・8・0%。「親・近親者の持家」同18・4%・17・5%・26・6%。 (4)収入状況―総計では単収入世帯45・2%、本人賃金収入と配偶者収入39・5%、その他14・7%。配偶者収入ありは男性50・3%、女性50・3%。配偶者の収入形態はフルタイムが総計41・1%、男性38・5%、女性64・1%。パートは総計28・8%、男性33・0%、女性2・9%。 1.賃金収入の状況 (1) 税込み賃金収入と家計 (1)昨年より低い賃金収入―08年9月で税込賃金収入は(税・社会保険料、天引き貯金、組合費などを含み、超過勤務手当、通勤手当、諸手当を合わせ月内に支給されたすべての賃金の合計)が36・0万円(総計)。これは昨年にくらべ▼2万円・6%。年齢中央値が1歳低いことを差し引いても、賃金水準は大きく低下した。 年齢別にみると男性は25歳未満で20・0万円、55歳以上が48・0万円。賃金カーブとしてみれば、その差は2・4倍。女性は同じ年齢層でそれぞれ18・0万円、45・5万円で、その差は2・53倍になる。女性の税込み賃金収入の水準は、いずれの年齢層でも男性より低いが、これは〈属性〉に見みるかぎりでは、家族構成・収入構造の差異による諸手当の差および学歴免許(による昇格・昇任)の差異によるものか。 (2)家計費下回る〈手取賃金〉―税・社会保険料を差し引いた〈本人手取り賃金〉は中央値・総計で28・9万円と昨年より1・7万円低い。男性は30・8万円、女性は30・0万円となる。これは家計費より低い水準であり、家計費との差はそれぞれ1・1万円・0・8万円・7・5万円となる。 なお、本人税込賃金収入に対する税・社会保険料の“公租・公課負担の割合は、総計で19・7%。賃金収入に対する公課負担率は男性の各年齢層で19%前後から22%を超える。もっとも負担割合が高い年齢層は男性では50歳代後半の23・3%、女性は50歳代前半で25・0%になる。 (3)賃金収入は11年前水準を下回る―これらを1997年からの経過でみると、この間の賃金停滞・水準の低下が際だつ。現状は、本人賃金収入も世帯総収入も手取り賃金も1997年以来もっとも低い水準にあることになる。この間、年齢・勤続年数の中央値は、年齢が38・5歳から40・5歳(40・5歳は07年、その他の年度では38・5歳から39・5歳、勤続年数は15・5年から17・5年)。 例えば11年前の1997年に本人の税込賃金収入38・2万円・手取り賃金31・1万円は、2008年に36・0万円・28・9万円。年齢中央値は38・5歳と39・5歳、勤続年数中央値は17・1年と17・5年。つまり11年前に比べ年齢も勤続年数も増えているのに対し、税込賃金で2・2万円、手取賃金で2・2万円も低い。 近年、人事院勧告における賃金引き下げ・賃金カーブ「フラット化」による中堅層以降の賃金抑制や2005年給与制度見直し(賃金水準引き下げと「現給保障」)によって、各自治体・公営企業賃金も引き下げられ、地方財政逼迫を理由とする賃金削減措置などが続いた。生活実態調査にみる賃金水準の低下は、この間の総人件費抑制の苛烈さをあらためて示している。 (2) 「ゆとりある生活のための必要な手取り賃金」 「ゆとりある生活のための必要な手取り賃金」について今回調査でも設問した。 賃金収入から公租公課負担を差し引いた「手取り賃金」に対する家計費をみると、ほとんどの年齢層で余裕がなくなる。 では、「手取り賃金」と「ゆとりある生活のための必要な手取り賃金」との差はどうか。男性年齢別では、40歳代前半で▼8・7万円。女性年齢別では同じく40歳大前半で▼10・1万円と差が大きい。総計では▼7・5万円となる。 ところで、この「ゆとりある生活のための必要な手取り賃金」が、昨年に比べて総計では▼3・1万円である。男性は▼2・3万円、女性は▼0・8万円。男性ではほとんどの年齢層で昨年より低く、例年に比べるなら“控えめ”な「必要手取り額」といえるか。 (3) 年収(世帯総収入) (1)中央値は683万円― 昨年1年間の同一生計世帯でみた世帯総収入としての年収は、総計で中央値683万円・平均値は703万円になる。昨年よりそれぞれ▼16・7万円、▼5・1万である。 男性でみると、中央値は676・7万円・平均値は694・6万円、女性はそれぞれ783・3万円、776・6万円である。昨年と比べ、男性は中央値で▼21・6万円、平均値▼9・7万円、女性はそれぞれ▼67・1万円、▼28・3万円と大幅な減収である。 年齢別の世帯総収入(中央値)を男性では、24歳以下の364・6万円が20歳代後半では433・3万円となり、30代前半では514・7万円、同後半では621・4万円、40代前半では706・8万円、同後半では783・3万円、50代前半では824・2万円、同後半では826・4万円となる。 一方、女性の世帯総収入(中央値)では、30代前半では655・6万円だが、同後半では881・8万円、50代後半は1180万円である。フルタイムの共働き世帯の多い女性世帯は30代以降になると男性世帯を大きく引き離すことになる。 (2)世帯総収入と本人収入 世帯総収入に占める本人収入比をみると、総計では、「10割」すなわち本人収入のみの世帯は42・7%と、半数を大きく下回る。ついで「9割くらい」12・2%、「5割くらい」8・9%、「8割くらい」8・8%、「6割くらい」7・4%、「7割くらい」7・0%、「4割くらい以下」9・2%で、この平均値は“約8割”、中央値は“約9割”となる。 本人収入比を男女別にみると平均値で男性(8割強)と女性(6割未満)では20ポイント以上の差がつく。女性で比較的高い世帯総収入となるところだ。また男性年齢別では加齢に伴ない本人収入比率がやや増加するが、30歳代以降は“8割”台の構成比にある。 2.昨年と比べた生活 昨年の今頃と比べた生活については、「苦しくなった」「非常に苦しくなった」をあわせた〈苦しくなった〉は総計59・1%で昨年の58・5%を上回る。一方、「かなり楽になった」「少し楽になった」の〈楽になった〉総計2・4%。 2000年に比べると〈苦しくなった〉は、総計で48・8%→58・5%、男性で50・7%→60・2%、女性で30・8%→38・0%に増加。年齢別では、男性の中堅層以上で〈苦しくなった〉が10ポイント前後も増えている。本人賃金収入の減少と世帯の年収の大幅な低下が生活を直撃した。 連合総研が民間企業労働者を対象に08年10月に実施した「勤労者短観」によっても、“景気の現状・1年後の見通し”をみた景況感は、特に4月時点に比べて急激に悪化、「悪くなった」80・0%、「悪くなる」55・8%と「調査以来最大」の“悪化判断”を示した。また“暮らし向きの現状・見通し”では「1年前と比べて悪くなった」35・7%、「今後1年間で悪くなる」38・1%で、「悪化」の判断・予測がいずれも2001年以降もっとも多い。 賃金水準の低下・停滞が続き、9月以来の「世界金融恐慌」の中、生活の逼迫感は強まりつつあるか。 3.生活全体について 全水道組合員が、現在の生活を全体としてどのように評価しているだろうか(設問は、「日頃のご自分の生活全体をふりかえってみてどうですか」)。 「まあまあだ」が総計45・3%で最多。男性43・8%、女性58・8%である。ついで「やや不満」38・6%、男性39・6%、女性30・3%が続く。「大いに不満」は総計10・1、%男性11・0%、女性2・1%、「かなり満足している」2・8%、男性2・4%と少ないが、女性やや多く6・1%である。“満足度”は男女で異なり「やや不満」「大いに不満」も男性より少ない。また女性での最多は「まあまあだ」58・8%で男性45・3%より13ポイント高い。 これを〈満足〉(「かなり満足」+「まあまあ」〉と〈不満〉(「やや不満」+「おおいに不満」〉でみると、総計で48・1%:48・7%。男性46・2%:50・6%、女性64・9%:32・4%で、総計・男性では〈不満〉が〈満足〉を4ポイント程上回る。 これを時系列でみてみよう。総計では〈満足〉が2000年57・5%→2005年46・7%→2006年49・7%→2007年45・6%→今回48・1%に対し、〈不満足〉2000年41・7%→2005年50・9%→2006年49・0%→2007年52・3%→今回48・7%と推移している。2005年以降は〈満足〉が過半数を割り込み、〈不満足〉は50%前後を推移。今回は2000年に較べ10ポイント以上高く、昨年より3ポイント程低くなっている。〈不満足〉が全体の半数を前後する傾向は2005年以来続いている。 男性年齢別みてみると20歳代前半では〈満足〉が77・7%ともっとも高く、30歳代で5割前後、40歳代から4割以下となり50歳代後半では〈満足〉33・4%ともっとも少ない。 一方、〈不満〉は40歳代前半から50歳代前半で6割前後となり40歳代後半では〈不満〉は63・0%ともっとも大きい。中高年層の抱える生活課題とこの間の賃金抑制などが生活満足度の押し下げ要因であるか。 この年齢層で〈不満〉が増加する傾向は時系列でみるとより明確になる。08年を2000年と較べると25歳未満で〈満足〉は77・7%:60・2%と増加しているが、30歳代以降は2008年は2000年に比べ〈満足〉が大きく減少、50歳代前半では33・4%:57・1%、50歳代後半では44・8%:66・6%と20ポイント以上も減少している。このため〈不満〉も20歳代では08年は2000年より〈不満〉が減少しているが、年齢とともに〈不満〉が増加し、特に40歳代後半で63・0%:47・2%、50歳代前半で62・9%:41・5%と15ポイント~20ポイント以上も〈不満〉が増加。 全水道組合員の生活評価の〈満足〉は世論調査の〈満足〉を大きく下回る。2008年調査の内閣府政府広報室「国民生活に関する世論調査」では、〈満足〉(「満足している」8・0%+「まあ満足している」52・4%):〈不満〉(「やや不満だ」28・2%+「不満だ」10・2%)が60・5%:38・4%。昨年は62・7%:36・0%であった。政府調査においても昨年と比べ〈満足〉が減少し〈不満〉が増加しているわけだ。 4.職場生活の諸側面 ―職場・職域の将来展望に〈満足〉12・4%のみ 職場生活の諸側面について15の課題別に評価を尋ねた。課題のそれぞれについて5段階(「かなり満足」から「大いに不満」)評価で回答を求めている。 「かなり満足」と「まあまあだ」を〈満足〉とし、「やや不満」「大いに不満」を〈不満〉に区分してみると、総計では〈満足〉がもっとも多い課題は、「労働時間や休日休暇の水準」54・0%。ついでほぼ同程度に」「職場の人間関係」53・0%、「友人・知人とのつきあい」49・6%「家族の健康状況」46・5%、「自分の健康状況」45・4%、「住居水準や住環境」41・2%「仕事のやりがい」39・9%、「職場の福利厚生」32・4%、「余暇・レジャー水準」31・7%とつづく。一方〈不満〉が多い課題は「老後への備え」66・2%、「わが家の貯蓄水準」60・3%、「賃金水準」59・2%、「職場・職域の将来展望」48・7%、ついで「職場の福利厚生」34・3%となる。 主な項目について、2000年との比較で〈満足〉が増えているのは、「職場の人間関係」が1・5ポイントで微増。他の課題についてはすべて〈満足〉が減っている。特に「賃金水準」は2000年24・2%→15・7%で▼8・7ポイント、「公務員としての身分確保」は▼8・3ポイント、「労働時間や休日休暇」は▼4・7ポイント、「職場・職域の将来展望」▲4・2ポイント。 一方、〈不満〉は「賃金水準」59・2%がもっとも多く2000年の59・4%と同水準。ついで「職場・職域の将来展望」48・7%で9・6ポイントの〈不満〉増加。その他に〈不満〉が増加している課題は、福利厚生では10・0ポイント、「公務員としての身分の確保では9・7ポイント増だ。他の課題では3ポイント前後増加している。〈不満〉が減っている課題は「職場の人間関係」のみが▲1・5ポイントである。 08年について〈労働条件〉、〈職場と仕事〉〈雇用の安定〉で区分し“満足と不満”をみてみる。課題別にみた全体の結果の特徴は次の様になる。 ●労働条件(賃金水準・労働時間や休日休暇・職場の福利厚生) [賃金水準]は、総計で「かなり満足」:「まあまあ」「やや不満」:「大いに不満」は、1・2%:14・5%:34・3%:24・9%で「どちらともいえない」が23・2%。「大いに不満」の大きいことが目立つ。男性年齢別にみると、特に20歳代前半で〈満足〉が24・5%と比較的高く、「まあまあだ」は23・4%、「どちらともいえない」は26・6%でもっとも多い。 とはいえ、〈不満〉が48・9%と半数に近く、「やや不満」31・9%がもっとも多い傾向は各年齢層と共通している。一方、中高年層では〈不満〉は高く、40歳代後半で67・9%に及ぶ。特に「大いに不満」は32・1%ともっとも多くなっている。年功的賃金カーブを残していると言われる公務員においても、数年来の賃金抑制と給与構造見直しによる賃金カーブのフラット化さらには評価制度の導入などが、とりわけ中高年層の賃金水準の低下・停滞となっている。また同時に年齢に関わりなく大きな不満をもたらしている。 [労働時間や休日休暇の水準]は同12・7%:41・3%:14・8:5・7%で、どちらでもないは23・2%、「まあまあだ」で4割以上となっている。また、「かなり満足」は1割を越え各項目の中でもっとも多い。 [職場の福利厚生]は同4・3%:28・1%:21・6%:11・1%。「どちらともいえない」33・1%がもっとも多いが、評価は割れているといえる。 これを性別、年齢別にみると、20歳代での〈満足〉が目立つ。40歳代以降は〈不満〉が目立つようになる。 〈労働条件〉について性別でみてみると、賃金水準、労働時間、福利厚生のいずれの課題でも男性に比べて女性の〈満足〉は多く、〈不満〉は少ない。それぞれの〈満足〉について男性:女性の比は、賃金で14・2%:28・7%、労働時間で52・7%:65・4%、福利厚生で30・8%:47・3%。一方、〈不満〉は、賃金61・6%:39・9%、労働時間21・1%:16・5%、福利厚生34・3%:20・2%となる。特に賃金についての〈満足〉は、男性は女性に較べ14ポイント以上低く、〈不満〉は20ポイント以上も高い。また、女性では、「まあまあだ」が男性より14ポイント高い。女性においては〈不満〉は多いが、評価は割れているともいえる。これはフルタイムの複収入世帯が多い女性では、例年の傾向である。 ●職場と仕事(職場や職域の将来展望・仕事のやりがい・職場の人間関係) [職場や職域の将来展望]は総計で〈満足〉は少数の13・8%で〈不満〉48・7%と半数に近い。「どちらともいえない」は35・4%。 一方、[仕事のやりがい]では〈満足〉が39・9%と約4割、一方で〈不満〉21・7%と2割強と比較的少ない。 「どちらともいえない」は35・4%ともっとも多い。「職場や職域の将来展望」への不満に対し、仕事にやりがいの〈不満〉が少なく、〈満足〉が多くなっている職場の現状に注目したい。 さらに、[職場の人間関係]はもっとも〈満足〉が多く53・0%と過半数。一方で〈不満〉は13・8%でこれは「友人・知人とのつきあい」にほぼ並んでもっとも少数となる。「どちらともいえない」31・6%で、「まあまあだ」が43・9%。 これらを性別・年齢別にみてみる。 〈満足〉について男性と女性の差は、[職場・職域の将来展望]3・6ポイント、[職場の人間関係]で14・6ポイント、いずれも女性が上回っている。 これらの課題は、男女とも入職後、間もない24歳以下で〈満足〉が最も多いが、加齢とともに減少。特に「職場・職域の将来展望」では〈満足〉が20歳代前半の36・2%に対し、50歳代後半では8・2%にまで低下している。この間のいわゆる公務員バッシングや職場の仕事の合理化・委託攻撃が将来展望に影響しているか。 [仕事のやりがい]で、男女ともに入職時に近い20歳代前半で〈満足〉が多く男女とも過半数を占める。ただ男性では、40歳代以降に〈満足〉は30%台となる。ここでも行財政改革による給与・人事制度の見直しや業務のアウトソージング化が仕事のやりがいにも影響しているだろうか。 ●雇用の安定(公務員としての身分・雇用の安定) [公務員としての身分の安定]は総計で評価が割れ、〈どちらともいえない〉39・4%が最多。〈満足〉29・7%、〈不満〉29・3%。 一方、[雇用の安定]は、「どちらともいえない」39・4%で、比較的〈不満〉23・0%と少なく、〈満足〉40・0%。ただしそれでも4割である。〈満足〉は男女ともに入職後から20代でもっとも多くなる。 これらの生活課題は、〈不満〉というよりは生活の先行き“不安”に関連している。生活全体の評価で若い層に〈満足〉が比較的高い理由に、これらの課題について〈満足〉が高いことの反映があろうか。 いま、公共サービスのあり方やセーフティネットなど社会システム再構築が問われている。公務員制度改革も基本権の進展はなお途上にあるが、労働諸条件の切り下げが続く中で、不安がかえって高まっていること示しているだろう。 図1 図2 図3 図4 図5 図6 図7 図8 図9 図10 表1 |
|||||||
| (トップへ戻る) | |||||||